Contents
経済産業大臣登録 中小企業診断士
船越ビジネスコンサルティング代表
船越です。
ビジネスに携わっている人であれば、マーケティングに興味がある人は多いと思います。
そして、世の中のマーケティングの解釈は「データ分析」「リサーチ」「販売促進」「テレビや新聞宣伝」等、多種多様であるのが現状です。
Wikipediaではマーケティングのことを、” 企業などの組織が行うあらゆる活動のうち、「顧客が真に求める商品やサービスを作り、その情報を届け、顧客がその価値を効果的に得られるようにする」ための概念である“ と定義されております。
そして、ドラッカーは、” マーケティングの理想は、販売を不要にするものである“ と述べており、他方では、”売れる仕組みを構築すること” とも言われているのです。
上記のように様々な解釈がありますが、マーケティングを難しく考える必要はありません。
「マーケティング」とは、簡単に言えば、” 売上を作るための活動全般“ のことなのです。
でも、世の中に出回っているマーケティング本て、難しくないですか?
例えば、コトラー、ポーター、ドラッカー。。
しかも分厚い本が多いです。
私は中小企業診断士で勉強し、様々なマーケティング本を読みましたが、正直、小難しい本を読まなくても、少しの簡単なマーケティング知識で、起業・週末起業・副業で売上を上げることが可能だと思いました。
ということで、今回は「売上を上げるためのマーケティング戦略」を解説していきます。
この記事を読めば、
- マーケティングの考え方
- マーケティングを簡単に理解する方法
- マーケティングの大切な要素
- マーケティングと同じぐらい重要なこと
以上のことが分かり、起業・週末起業・副業をされる方にとっては、売上を上げるヒントになるかもしれないので、是非とも読み進めていただきたいと思います。
マーケティングの考え方

マーケティングの考え方としては、 利益 = 売上‐費用 です。
利益が出なければ、成長するための投資や借入金の支払いが出来ませんし、そもそも企業活動を継続することができません。
そして、その利益の源泉が売上というわけですね。
なので、企業活動において、財務や資金調達、資金繰りなども重要な仕事でありますが、利益の源泉となる売上を上げるためには、同じくマーケティングも重要だということです。
例えば、設備投資にはいくらの金額が必要なのかは、「いつ何をどれぐらい売るのか」によって、投資時期や投資規模、投資する内容がかなり変わってきます。
IT投資は戦略的な決断が必要ですが、どんなIT投資を行うのかはマーケティング戦略によって決まります。
また、人材育成においても、どんな人材をいつ採用、育成するのかは、会社のマーケティング戦略によって異なります。
そして、マーケティング戦略の意思決定は、経営者にとって極めて重要です。
なぜなら、ここを失敗すると、単純に「売れない」状況に陥るからです。
つまり、マーケティングを理解しなければ、経営が継続できなくなる可能性があるということです。
マーケティングのイメージとは?

マーケティングの重要性は解説させていただきました。
では、これだけ大切であるマーケティングは企業、起業家、週末起業家等に浸透しているのでしょうか。
残念ながら、大手企業以外はマーケティングを重視していないのが現状です。
これは、私のコンサル活動でも実感しています。
重視しない理由は、そもそも中小企業や個人事業主は資金が不足しがちなので、まずお金に関することが重視されること。
結果、マーケティング戦略を考えている場合でもなく、時間もなければ、人材もいない状態なのです。(もちろん、マーケティングを考えている会社も個人事業主もおられます。)
そして、もう一つの理由として、マーケティングが難しく考えられており、とっつきにくいイメージがあることです。
例えば、
- 4P
- 3C
- SWOT
- STP(セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング)
- コア・コンピタンス
上記のマーケティング用語が何となく難しく、ある種の抵抗感・嫌悪感のようなものに起因することが考えられます。
でも、マーケティングって、そんなに難しいものなのでしょうか?
マーケティングが難しければ、誰しもが簡単に実行できませんよね。
でも、現実はマーケティング戦略を構築して、売上を増加させている会社は多くあります。
ただ、やっていることがマーケティングと知らずに結果的にマーケティングになっている会社も多くありますが。。
しかし、マーケティングは決して最先端技術の研究のレポートを理解するわけではないので、誰でも理解できるはずなのです。
勝手に難しくしている、難しく考えているだけなんですね。
なので、まずはマーケティングを簡単に考える必要があります。
マーケティングの大切な要素

決して、先ほどお伝えしました、SWOT等のマーケティング用語を理解して実行すれば、売上は上がるわけではありません。
ここでよくありがちなのは、マーケティング用語を理解したつもりで小手先のテクニックを駆使してしまうことです。
つまり、マーケティングを点で考え、戦略を無視した流行りのマーケティング方法だけで販売してしまうことです。
小手先のテクニックでは短期的に売上が上がったとしても、長期的には難しくなるでしょう。
なぜなら、戦略と販売方法に一貫性がない、ということになりがちだからです。
小手先のテクニックは、短期的に売上を上げる方法です。
なので、会社の方向性を無視しがちです。なぜなら、売る人間はどんな方法であっても売上は欲しいですし、会社も売上が上がるのであれば、どんな方法でもやめさせにくいからです。
そういう会社は、売れなくなれば、今度は違うテクニックを使って販売することになります。
大切なことは、マーケティングを点で考え、テクニックとして使うのではなく、面としてとらえ、一貫性を重視することです。
一貫性については後述しますが、マーケティングで必要となる要素は下記の5つです。
- 競合
- 強み
- ターゲット
- マーケット
- 経営資源
つまり、競合にはない、自社の強みを評価してくれる、お客様(ターゲット)が、どの市場(マーケット)に、いるのかを探す必要があります。
そのためには、まず、自社の強みを知ることが重要となります。
ここで気を付けなければいけないことは、強みは、「競合と比較しての強み」であり、競合と比較しない思い込みの強みでは、それは強みではない可能性があるということです。
例えば、自社の強みを「多品種少量生産が可能」と思い込んでいても、競合も同じことが可能であれば、それは強みではなく、それが普通だということです。
なので、強みを知るには競合を知らなければなりません。
競合を知り、自社の強みを知れば、次に自社の強みを評価してくれる顧客(ターゲット)、市場(マーケット)を探しましょう。
そして、その顧客に対して、どういった商品(サービス)をいくら(価格)で、どうやって販売するのかを決めます。
その顧客に対して、自社の強みを評価してもらうための販売促進をする必要があります。
また、自社の強みが、簡単に競合他社に真似されては、強みではなくなります。
なので、自社の強みは自社の経営資源から成り立っている必要があります。
例えば、アパレル会社の強みが「接客力」であるとき、その源泉が、独自の販売員育成システムにあることです。
この販売員育成システムが経営資源になるのです。
他社は接客方法を簡単に真似ることができますが、販売員育成システムは、外に見えるものでもないので、簡単に真似ることができません。
真似ただけの接客では、育成システムがないので、個人差がでてきます。
それでは、スタッフによって顧客満足度がかなり違ってくるわけですね。
なので、結局お客さんはスタッフに個人差がある店より、スタッフ皆が同じだけの接客力がある店を選ぶようになります。
また、新しいスタッフが入っても、接客力があるスタッフに育つため、長い目で見れば、他店に接客では負けるわけがありません。
この独自の育成システムである経営資源こそが、難しく言うと、コア・コンピタンスなのです。
お気付きの方もおられるとは思いますが、今まで説明したことは、上記で述べたマーケティング用語である、SWOT、3C、STP、4Pをほぼ網羅しています。
つまり、マーケティング用語を難しく考える必要がないということです。
でも、中には「SWOTの他の要素である、弱み・機会・脅威は気にしなくていいの?」
と思われる方もおられるかもしれませんが、とりあえずは必要ありません。
大企業ならともかく、それ以外の会社であれば強みを見つけ、伸ばす方が早いですし効率的です。
強みを伸ばし競合に勝つことができれば、極論を言えば、それ以外の外部環境も気にする必要はありません。
気にしてもしょうがないですからね。
マーケティングには一貫性が大切

マーケティングの要素として、競合・強み・ターゲット・マーケットについて説明をさせていただきましたが、さらに大切なことはこれらに一貫性があることです。
成長している会社はマーケティングを理解しており、さらに一貫性があります。
なぜ、一貫性が大切なのか?
私に相談に来られた、飲食店のオーナー夫婦を例に、簡単にご説明しますね。
そのお店の強みは、手の込んだ料理・サービスとリピーターの存在です。
狙う市場は、ゆっくりと美味しく食べられる場所、ターゲットは、食事にこだわる地元住民です。
しかし、徐々に客数が減少し、結果、売上も厳しい状態でした。
そこで、お店のオーナーが考えた方法は、「新規顧客を呼び込むために、新規の方のみ安くなる割引券を近所にポスティングする」というものでした。
この方法は、短期的には売上が向上するので、売上が厳しい時にどこのお店もよくやりがちです。
しかし、戦略が一貫していません。
新規客のみに割引券を渡してしまうと、リピーターである既存客はどう思うでしょうか?
私がリピーターであれば、嫌な感じがします。
なぜなら、リピーターであるにもかかわらず、損をしているうえに、雑に扱われている気がするからです。
常連さん・リピーターは、自分を特別扱いして欲しいと思ってますし、ある意味それは当然だとも思っています。
なので、もし、軽いあしらいを受けると、怒るか黙って去ってしまうでしょう。
また、商品(サービス)を安く提供するようになってしまうと、売上を上げるためには、客数をさらに増加させなければなりません。
そうなると回転率を上げる必要があり、今まで通りにゆっくりできなくなります。
結果、既存顧客、リピーターが減少するのです。
つまり、商品単価を下げることで短期的には売上が上がるかもしれませんが、固定客が離れ、長期的には経営が悪化することになります。
なので、こういった目先の利益に走る戦略は避けた方が良いです。
そこで、相談者とお話をして戦略を見直すことにしました。
行ったことは、下記です。
- 既存顧客の接客強化
- メニューの変更
- 商品の試食、試飲
簡単に説明すると、既存顧客の好みを把握し、接客対応する。
また、手の込んだ料理を見やすくするためにメニュー表の変更を行いました。
そして、おすすめ商品をさりげなく試食、試飲してもらい追加オーダーをもらう仕組みを構築。
結果、オーダー数が増え、顧客満足度も高まったため、客単価と来店頻度が増加したのです。
上記のように、「強みを理解してくれる顧客」を取り込む。
言われてみれば当たり前なことなのですが、現実はそうではないのです。
例えば、ブランド力が強みであるアパレルショップのセール乱発です。
このように、一貫性のないマーケティング戦略は、自社の強みを自ら打ち消しているため、長期的に見れば企業を衰退させることになります。
そして、一貫したマーケティング戦略によって、各分野で行うことが決まります。
先ほどの飲食店を例にしますと、接客人材を採用する場合、テキパキとこなすタイプより、気の利いたサービスが提供できる地元の人が基準となります。
販促も自社の強みを評価してくれる顧客に向けたものとなり、リピーターを増加させるための方法を採ります。
IT戦略においては、新規顧客向けではなく、既存顧客・リピーターのためのSNSコミュニティの提供等、を行うことになります。
このように、戦略が一貫していれば、各分野で行うことが明確になるのです。
マーケティングと営業の関係性
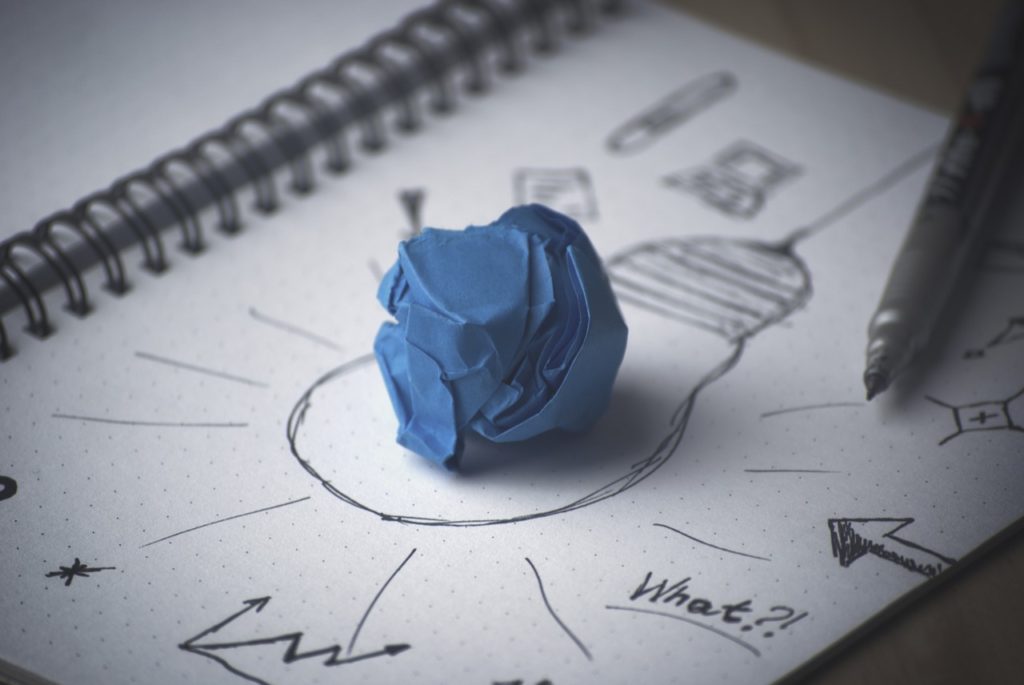
マーケティングと営業は非常に密接な関係にあります。
ただ、マーケティング=営業ではありません。
マーケティングの中に営業が含まれるイメージですが、まずは、そもそも論である「営業とは何かについてご説明しますね。
営業とは
会社を経営していくうえで、利益を上げるために必ず必要になってくるものが「営業活動」です。
しかし、営業とはそもそも何でしょうか?
当たり前の言葉だけに、その意味を深く掘り下げることはあまりないですが、営業とは、簡単にいえば継続的に自社のモノ・サービスを売る行為を意味します。
なぜ、モノ・サービスを売るのか?といえば、会社としての利益を得るためです。
つまり営業とは、経済活動の基本であると言えるでしょう。
営業戦略の重要性
経済活動の基本である営業の役割は重要ですが、営業活動において営業戦略はさらに重要となります。
会社の営業戦略を考えるのは社長です。
社長が戦略を考え、数字に落とし込み、営業員に理解させ、行動させる必要があります。
しかし、考える時間がないとの理由で、戦略が存在しない場合、営業員は誰に何をどのように売ればいいのか分かりません。
結果、営業員が勝手にターゲットと違うお客様に販売したり、安く販売したりしてしまいます。
なので、営業戦略がないために個人の力量に頼り、業績が悪化する会社の話はよくあります。
つまり、個人の力に頼らない、勝手な販売をしないためにも営業戦略は重要と言えます。
現在の営業に求められること
現在において、営業はただ単にモノ・サービスを売ればいい時代は終わりました。
営業論となると、コミュニケーション能力や自己管理能力、行動力等が話題になります。
しかし、現在の営業にはこれらの能力に加えて、会社の営業戦略を理解し、戦略に沿った売上を上げる方法を考え、実行する力が必要なのです。
営業で売上を上げる方法とは?
では、営業で売上を上げる方法とは何でしょうか。
まずは、売上を構成する要素を分解する必要があります。売上とは、
売上 = 客数 × 客単価
次に、客数を分解します。
客数 = ( 既存客 + 新規客 - 流出客 )
そして、客単価を分解します。
客単価 = 商品単価 × 商品数 × 購入頻度
となります。上の3つの式を統合すると、
売上 = ( 既存客 + 新規客 - 流出客 ) × 商品単価 × 商品数 × 購入頻度
となり、売上を上げる5つの要素が導き出されます。
結果、売上を上げる方法は5つとなります。
- 新規客を増加する
- 流出客を減少させる
- 商品単価を上げる
- 商品数を増加させる
- 購入頻度を増加させる
この中で優先順位が高いことは、2の既存客を流出させないことです。
新規客と流出客を比べると、新規客を獲得する方が数倍難しいと言われています。
コストで換算すると新規客の獲得は流出客の減少よりも5~10倍コストがかかると言われています。
新規客を増加させる前にまず、既存客を流出させずに、既存客に必要とされること。
既存客に必要とされていない状況で、焦って新規客へ営業しても、基盤の商品(サービス)や組織が整っていなければ、いずれ失敗します。
そして既存客に対して、商品単価を上げても買ってもらえる商品(サービス)を強化するのか、購入数を増加させるのか、頻度(リピート率)を上げる施策を採るのかを決めるべきです。
以上となりますが、現在置かれている状況によって、どの方法を採るべきかが違います。
まずは現状を分析し、営業戦略を考え、1~5のどの方法を採るべきかを決定しましょう。
売上が苦しい局面で営業に必要なこと
売上がかなり厳しく、経営が苦しい時は少し状況が変わってきます。
売上が悪化している状況では営業員の士気が相当下がっていることが想定されます。
そういう時はいくら戦略を練って、数字を作っても、営業員に売る気がなければどうしようもないのです。
なので、そんな状況時は、経営者が営業員の士気を上げられるかどうかにも、会社の今後がかかっているのです。
営業を強化する方法
マーケティング戦略は、営業の戦術レベルの施策を統括する、ガイドライン的存在となります。
どのような場所、相手に販売するのか、どのような販促を打つのか、という各施策は、「誰に、何を、どのように、どうやって」というマーケティング戦略に依拠します。
当然ながら、ターゲットによって、価格、チャネル、販促施策等が全く違うため、もし営業が自社のターゲットを間違っていれば、販売する方法が変わってくるわけです。
なので、営業を強化するには、まず、自社のマーケティング戦略を営業が理解することが重要となります。
そして、戦略を数字にします。
売上計画をたて、その売上を達成するために、客数・客単価のどちらを重視するのかを決め、具体的なアクションプランを考えます。
そして、そのアクションプランを実行、結果を評価し、戦略を修正するPDCAサイクルを回せば、営業が強化されていくのです。
【参考記事】事業計画とは何か?必要性を理解し、自分自身の計画も作成しよう!
マーケティングの前に重要なこと

マーケティングは冒頭の方で、”売ることの関する全てのこと” と言いました。
ということは、売る商品(サービス)があるという前提の話になります。
つまり、マーケティングの前にビジネスモデルが必要となるのです。
マーケティングが活躍するのは、ビジネスモデルを構築してからになります。
例えば、年配者がホームページを制作できるパッケージングモデルで事業を始めようとする、「でも、これをどうやって販売していけばいいのか分からない。」
ここで登場するのがマーケティングですね。
なので、たとえマーケティング戦略が優れていても、元々のビジネスモデルがめちゃくちゃであれば、猫に小判状態となります。
極端な例でたとえると、「銃を高齢者の安全のために販売するビジネスモデル」。
そもそも法律に反しているので、マーケティングで頑張っても裏社会ぐらいにしか販売できないですよね。極端すぎてすみません。笑
逆もしかりです。
いくらビジネスモデルが優れていても、マーケティングが機能しなければ、優れたビジネスモデルがもったいない状態となります。
なので、マーケティングとビジネスモデルは切っても切れない関係なのです。
つまり、ビジネスモデルとマーケティング、どちらもビジネスをより効率的に進めていくには、欠かせないものとなります。
なので、まずは優れたビジネスモデルを構築してから、マーケティングに取り掛かりましょう。
【参考記事】起業・副業したいけどビジネスモデル・アイデアがない人は何をすべきか?
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は簡単なマーケティング知識を身につけて売上を上げる方法について解説を致しました。
自社の強みを評価してくれる顧客、市場を探し、顧客のことを考え、顧客が必要としているものを提供できれば売上は必然と上がります。
本当にお客さんのことを考えれば解決するはずです。
お客さんのことを考えているつもりでも、自社都合で施策を行っていることが多いのが問題なんですね。
でも、
「自社には大した強みがないし。。」
と言われる社長もおられますが、必ず強みはあります。
強みが見つからなければ、もう一度探しましょう。
何度も探しましょう。
それでもないのであれば、強みを作りましょう。
そして、この記事を読んだ結果、マーケティングを理解し、売上が増加するためのヒントを得ていただいたのであれば幸いです。












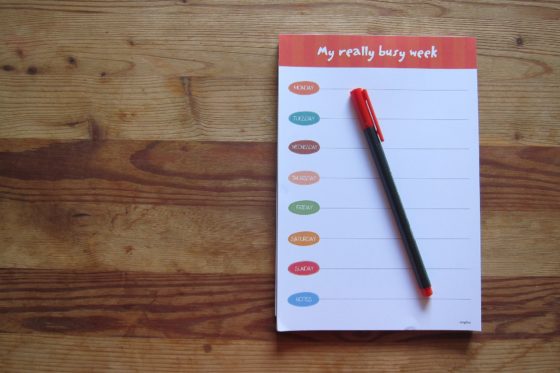






コメントを残す